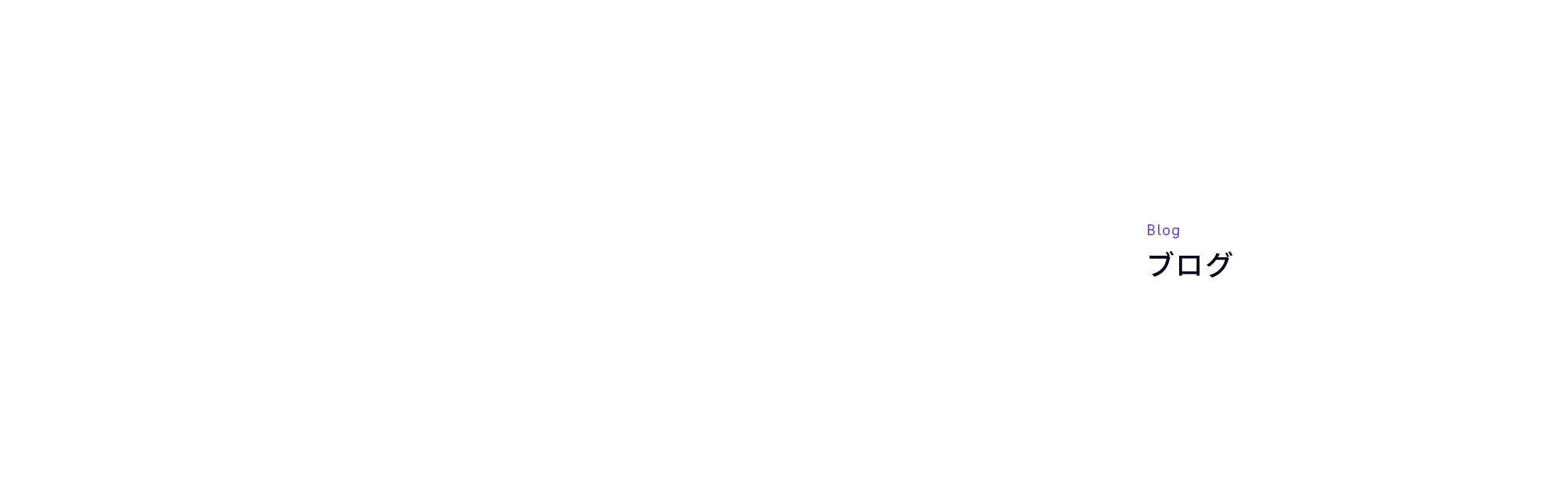皆さんこんにちは!
シニアコート菜康苑、更新担当の中西です。
さて今回は
年末だからこそ大切にしたい、介護施設の「あたたかさ」🎄
12月は心が少し忙しくなる季節
12月は、クリスマスや年末年始などの行事が重なり、
一年の中でも特に慌ただしく感じやすい時期ですよね。
街はイルミネーションでにぎわい、
テレビでは「今年の振り返り」や「年末特番」が流れ、
自然と「もう一年が終わるんだな」と感じる季節です。
ご利用者さまにとっても12月は、
いつも以上に心が動きやすい時期でもあります。
-
「今年は家族に会えるかな」
-
「この一年、いろいろあったな」
-
「また一つ年を重ねるんだな」
そんな思いが、ふとした瞬間に浮かぶことも少なくありません。
だからこそ、介護施設には
**いつも以上の“あたたかさ”や“安心感”**が求められる季節だといえます。
何気ない声かけが心を支える
年末だからといって、
特別なことをしなければならないわけではありません。
実は、ご利用者さまの心を一番支えているのは、
毎日の何気ない声かけだったりします。
-
「寒くなりましたね」
-
「今日は少し風が冷たいですね」
-
「今年もあと少しですね」
-
「体調はいかがですか?」
こうした一言一言が、
「ちゃんと気にかけてもらえている」
「ここにいて大丈夫なんだ」
という安心感につながっていきます😊
日常の延長にある、さりげない会話。
そこにこそ、介護の原点である人のぬくもりがあります。
忙しい年末だからこそ、
ほんの数秒の声かけが、大きな意味を持つのです。
年末行事は「無理なく・楽しく」
12月はイベントが多い季節ですが、
大切なのは「頑張りすぎないこと」。
ご利用者さまにとっても、職員にとっても、
無理のない形で季節を楽しむことが一番です。
例えば、
-
クリスマスの飾り付けを少しだけ🎄
-
いつもより少し特別なおやつ🍰
-
みんなで懐かしい歌を口ずさむ時間🎶
大掛かりなイベントでなくても、
十分に「12月らしさ」を感じていただけます。
「楽しかったね」
「季節を感じられてうれしい」
そんな一言が聞けるだけで、
その時間は大切な思い出になります。
気持ちが揺れやすい時期だからこそ
年末は、楽しい行事がある一方で、
少し寂しさや不安を感じやすい時期でもあります。
-
家族と過ごせない寂しさ
-
体調への不安
-
これから先への心配
そうした気持ちが、
普段より表に出やすくなる方もいらっしゃいます。
だからこそ、
介護施設の職員がそばにいること自体が、
大きな支えになります。
「今日はどうしましたか?」
「何か気になることはありませんか?」
そんな声をかけられるだけで、
心が少し軽くなることもあるのです。
ご家族にとっても安心できる場所であるために
年末は、ご家族にとっても忙しい時期です。
仕事や家のこと、帰省の準備などで、
なかなか面会に来られないこともあります。
だからこそ、
「ここに任せていれば安心」
と思っていただける存在であることが、介護施設には求められます。
-
普段の様子をさりげなく伝える
-
表情や体調の変化を共有する
-
小さな出来事も大切にする
こうした積み重ねが、
ご家族との信頼関係をより深めていきます。
まとめ
12月は、介護施設の本当の価値が伝わりやすい季節です。
特別なことをしなくても、
あたたかい声かけや、変わらない日常、
そして人と人とのつながりが、
ご利用者さま・ご家族・職員、
みんなの心をそっと支えてくれます✨
年末だからこそ、
改めて「介護のあたたかさ」を大切にしていきたいですね。
詳しくはこちら!